EOS R1とEOS R3のどちらが優れているか
EOS R1とEOS R3のどちらが優れているのでしょうか?記事では、それぞれの性能ごとに違いを説明し、最終的な結論を導き出しています。
- センサー
- 画素数は似ているがEOS R1の新開発のセンサーが搭載されている
- イメージプロセッサ
- EOS R1にはDIGICアクセラレータがあり、ディープラーニング技術による大量のデータ処理をサポート
- オートフォーカス、連射性能、画質が向上する
- ISO感度
- EOS R1の常用ISOの範囲がわずかに広い
- AF
- EOS R1には新しいデュアルピクセルインテリジェントAFが搭載されており、被写体の横断や上半身を検出、頭部を推定して障害物を回避する高度な追跡アルゴリズムを提供
- EOS R1にはアクション優先被写体追跡モード、登録人物優先モードが搭載
- 連射
- EOS R3は30コマ/秒、R1は40コマ/秒の連続撮影
- EOS R1にはプリキャプチャ機能が搭載
- ファインダー
- EOS R1はEOS R3より画素数が多い944万ドットのEVF
- 液晶
- EOS R3のほうが解像度の高い415万ドット背面液晶を採用
- ボディ内手ぶれ補正
- EOS R1のほうが補正効果が0.5段ぶん高い
- メモリカード
- EOS R3はSDスロットがあるが、EOS R1はCFExpressのデュアルスロット
- 価格
- EOS R1は6999ポンド、EOS R3は5799ポンド
結論
新しいEOS R1とEOS R3のどちらを選択するかは、EOS R1のデュアルプロセッサ技術とそれに伴うオートフォーカス、連続撮影、画質の向上が、あなたにとってどれだけ有益かどうかにかかっている。それ以外では、両者は非常に互角となっている。
というわけで、結論としては、進化したオートフォーカスの性能が必要かどうか、電子シャッターで10コマ/秒多く撮影できる連射性能が必要かどうか、デュアルプロセッサによる画質の向上が欲しいかどうかが決める要素だとしています。視線入力AFはどちらにも採用されている技術のため、比較対象にはならなかったようですね。
やはりEOS R1の魅力は被写体となる人物を登録できたり、アクションを予測してフォーカスを合わせたりなど、AI技術によるオートフォーカスの向上というところが大きいのかもしれません。
しかしEOS R1でオールクロス測距になった部分についてはあまりレビューでも触れられていませんよね。それだけあまり違いがわからないということなのでしょうか?また、EOS-1D X Mark IIIクラスの耐久性、防塵防滴性能についても触れられていませんが、こちらはEOS R3にもある程度の防塵防滴性能があるからかもしれません。カタログスペック以外のところの違いが大きいため、なかなか直接的な比較は難しいという側面もあるのかもしれませんね。
さらに「EOS R1とEOS R3の決定的な違い それは妥協を許さないプロを対象にしていること」ではEOS R1とEOS R3の決定的な違いについて詳しくお伝えします。
(記事元)PhotographyBlog
| Nikon Z 9 | EOS R1 | |
| イメージセンサー | 4571万画素 裏面照射積層型 | 2410万画素 裏面照射積層型 |
| エリア全域でのクロスAF | - | 対応 |
| イメージプロセッサ | EXPEED 7 | DIGIC X + DIGICアクセラレータ |
| 常用ISO | 64-25600(拡張32-124000) | 100-102400(拡張50-409600) |
| フォーカスポイント | 493点 | 1053点 |
| メカシャッター | - | 対応 |
| 動画(最大) | 8K 30p、4k 120p | 6k 60p、4k 60p |
| EVF | 0.5インチ 369万ドット | 0.64インチ 944万ドット |
| 視線入力AF | - | 対応 |
| 背面液晶 | 3.2インチ 210万ドットタッチ式4軸チルト | 3.2インチ 210万ドットタッチ式バリアングル |
| ボディ内手ぶれ補正効果 | 6.0段 | 中央8.5、周辺7.5段 |
| 連続撮影(電子シャッター) | 20コマ(4570万画素、RAW) 30コマ(4570万画素) 120コマ/秒(1100万画素) | 40コマ(2410万画素) |
| メモリカード | デュアルCFExpress Type B/XQDスロット | デュアルCFExpress Type Bスロット |
| バッテリー | EN-EL18d | LP-E19 |
| シャッター速度(電子シャッター) | 1/32000~30秒 | 1/64000~30秒 |
| シャッター速度(メカシャッター) | - | 1/8000~30秒 |
| シンクロ同調(電子シャッター) | 1/250秒 | 1/400秒 |
| マイク端子 | 対応 | 対応 |
| ヘッドホン端子 | 対応 | 対応 |
| GPS | 対応 | 対応 |
| 最大画像サイズ | 8256×5504ピクセル | 6000×4000ピクセル |
| 測距可能輝度 | -7~19 EV | -7.5~21 EV |
| バッテリー寿命 | 700コマ | 530コマ |
| WiFi 6G | - | 対応 |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| サイズ | 1340g、149×150×91mm | 1115g、158×150×87 mm |
| 価格 | 店頭予想約70万円前後 | キヤノン公式108万9000円 |
[catlist tags=”canon” numberposts=10]







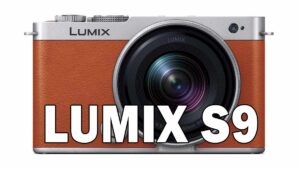

コメント
コメント一覧 (5件)
既にR3保有者は慌ててR1買い替えする必要ない気もするが、R3は2021/11発売で2年8ヶ月経過
来年後継機出る可能性高く、後継機のスペックと値段見てからR1にするかR3Ⅱにするか判断しても良い気がする
もしR3Ⅱがグローバルシャッターになり、R1より高いなら個人的にはR1勧める
値段は勿論100万円は超えるだろうし
しかしR1の改良版みたいな扱いで積層センサーならば80万以下にして来るだろうから、R1レベルのスペックが必要ないなら、アップスケーリング機能やAIノイズ低減使えて、場合によってはクロス測距AF搭載される可能性もあるので期待したい所
ただセンサー使い回ししない可能性もあり、24MPと45MPの中間の画素数設定してくると予想
そうやって差別化はかる
何を入れて何を外すのか
キヤノンは本心では部品共用化してコストダウンしたい思惑はあるにせよ、共用化し過ぎて差別化はかれないジレンマに陥るのも警戒してる
後はEVFのドット数をR5Ⅱと同じにするとか
最初からそんなにR1のセールスを期待してないならば、R3Ⅱが積層センサーならばかなり機能のてんこ盛りは期待出来る
しかもR1の月産台数は3,700台とコロナ禍明けのキヤノンとしてはかなり少ない設定
年間5万台にも満たない数字になるから
最初の1年で10万台近くは動くと思うけど
そうするとR3Ⅱ新発売の時期的に重なるからどうやって棲み分けするかどちらにしても興味深い
もっともR3をファームアップして、プリキャプチャー入れる程度の事はしても良いし、キャッシュバックしてR5Ⅱの実売価格のプラス5万円程度にすればまだ売れると思うけど
バッテリーグリップ代の5万は乗るけど、本体価格部分は同じだよみたいなメッセージ出して
だからキャッシュバック7万とかは必要
やるなら今年の冬のキャンペーンかな
コレからR3検討してる人なら、モデル末期で50万なら買いだけど、R5Ⅱに素直に行った方が賢いと思うわ
縦位置グリップがどうしても必要なら仕方ないけど、R5Ⅱ用の縦位置グリップも5万程度であるから
R3がファームアップあるかとキャッシュバックがいくらかなのか次第かな
それにR5Ⅱにも視線入力付いた事でR3の独占事項がかなり消えてる
本当はアップスケーリング機能が1番必要なのはR3だろうけど、それは多分無理でしょうね
だから余計にR5Ⅱ選択になる
概ねスケールダウンしたような性能なので廉価版R1として見れるのではないかと。”最新の”AF性能を求めなければ多くのユーザーにとってはまだまだ現役で使える実力を備えていると思います。
中古ならばR1のおおよそ半額で買えますからこれからしばらくはR3の中古市場が盛り上がると思います。
オールクロスAFは横線や斜め線が多い対象でのAFの合焦率を上げるので、
バスケットボールの撮影で全てにAFがあったという事がオールクロスAFの結果だと思われます。
ただ、これをレビューにするなら同じすスポーツ撮影でR3とR1のAF合焦率を出すことになり…マーケティングとしては歩留まりが発生した他機種下げになりそうなので、レビューは難しいのではないかなと思います。
製品版のR1が市場に出ていない状況で比較は難しいでしょうね。
クロス配置のDPCMOSも使ったことがないわけでレビューは
無理でしょう。
発売されてから様々なレビューが出るでしょうからその時に
考えればいいかなと思います。
すぐに必要なら R3しかありません。
DPCMOSも縦線が拾えない分けではなく交互に少し角度を
変えて配置しているので通常の撮影ではあまり困らないはず。
なんで急にz9のスペックシートが出てくる?