X100VとX100VIの画像比較
X100VとX100VIで撮影した画像を比較し検証する記事が話題となっています。ここでは、その検証記事について詳しくお伝えします。
X100VとX100VIの間では、三脚使用時にディテールの改善が顕著に見られる。大きな絞り値でもこれほどの違いがでるとは予想していなかったが、X100VIが優れているのは明らかで、三脚を使用する場合には買い換える価値がある。
カジュアルな撮影では、その違いは決定的なものではなく、現実の撮影条件で被写体ブレやボディ内手ぶれ補正の影響があると、違いには気がつかないかもしれない。
実際の撮影では解像度の違いはあまり感じない。もしかするとX100VIのレンズがピントをしっかりと合わせていないのかもしれない。しかしいつも感じるのはX100VIの細かく引き締まった粒状感が旧モデルよりも扱いやすいということだ。常にシャープネスが向上するわけではなくとも、日常の撮影では粒状感が引き締まっているので、2400万画素や2600万画素の富士フイルムのセンサーに対する最大の不満が解消されている。
X100VIの解像感が増している
X100VとX100VIで撮影した画像を比較する記事が公開されています。上記はまとめ部分を引用したもので、実際に撮影された画像や詳細な解説がありますので、全文は記事元リンクからご覧ください。記事元では分割線を横にスライドする形でそれぞれの画像を比較することができるようになっています。
まずはX100VとX100VIの機能の違いですが、解像性に最も影響すると考えられる違いはセンサーと画素数とイメージプロセッサの世代が違うところだと思います。
以下に主な仕様の違いをまとめておきますが、ご覧の通り4000万画素と2600万画素ということで、かなりの違いがありますね。
| X100VI | X100V | |
| 有効画素数 | 約4020万画素 | 約2610万画素 |
| 画像処理エンジン | X-Processor 5 | X-Processor 4 |
| 標準ISO | ISO125~12800 | ISO160~12800 |
| 手振れ補正 | 6.0段 | なし |
| 電子シャッター | Pモード: 30秒~1/180000秒 | Pモード: 30秒~1/32000秒 |
| 被写体認識 | 顔/瞳/動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車 | 顔/瞳認識 |
| 動画トラッキングAF | あり | なし |
| 背面液晶チルト角度 | 45度 | 30度 |
| 動画 | 最大6.2k 30p | 最大4k 30p |
| フィルムシミュレーション | 20モード | 17モード |
| WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n |
| バッテリー | EVF時約360コマ | EVF時約350コマ |
| 寸法 | 128.0×74.8×55.3mm | 128.0×74.8×53.3mm |
| 重量(バッテリー、メモリ含む) | 約521g | 約478g |
さて、記事では三脚を使用した場合には、その解像性の違いがよくわかるとしています。それはかなり絞った時でもわかるとしていますね。しかしスナップ撮影などカジュアルな撮影などでは、被写体ブレがあったり、ボディ内手ぶれ補正が働いたりして、そこまでの違いは実際にはあまり違わないだろうことを指摘しています。
個人的にはサイトのお札を撮影した画像を比較してみても差はよくわかりませんでした。唯一違いがわかるのは、1万円札の右下の花の模様(大小二つある円形の模様の小さい方)で、これを比較するとややぼやけているのがX100Vで、細かなところまでよく撮影されているのはX100VIであることがわかる程度です。
この他にも右側の白黒の放射状のテストパターンのより中央部まで判別できるほうがX100VIであることがわかりますが、それも本当によく見てわかる程度でぱっと見た程度ではまったく違いはわかりません。
というわけで個人的には2600万画素でも十分だなという印象です。ただもっと繊細なものを撮影するとか、三脚を利用して自然撮影するといった場合、クロップする場合には役立ってくれるのかもしれません。
皆さんにはどのように見えたでしょうか?
さらに富士フイルム関連記事「富士フイルムのX-M5の噂されている仕様 11月までに発表か!?」ではX-M5の仕様の噂について詳しくお伝えします。
(記事元)https://alikgriffin.com/fujifilm-x100vi-vs-x100v-sensor-resolution-comparison/
[catlist tags=”fujifilm” numberposts=10]







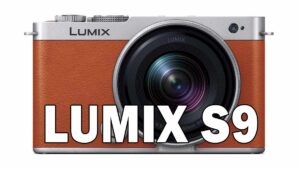

コメント